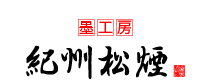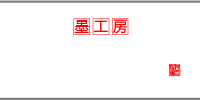小黒世茂の熊野よもやま話
| 昆虫食 | |
しょうゆをすこし浴びて寝て居り 佐々木幸綱『初めての雪』 昆虫学者が1919年に行った調査によると、そのころ日本では55種類もの昆虫がたべられていたという。 食虫のなかでは水田にBHCを撒くまでは、イナゴのつくだ煮が多くでまわったほか、地方によっては蜂の子〔クロスズメバチの幼虫〕、ザザムシ〔カワゲラの幼虫〕、ヒメエグリバ〔コウモリガの幼虫〕なども貴重な蛋白源として利用してきた。 ことにへぼ取り・スガレ追い・ジバチ取りともいう蜂の子取りは今も、長野県や岐阜県で盛んにおこなわれていると聞く。 刺されると死にいたる恐ろしい蜂も、その幼虫は噛むと香ばしく、バターに似たコクとミルキーな甘さが口いっぱいに広がるという。 へぼ取りは全身をくまなく使うスポーツだ。 秋の旬をねらい山の地形や獲物の習性をよく知るものを先陣に、大人達が5〜6人で山に入る。 働き蜂いっぴきの動きに対して全神経を集中させ、地下足袋や長靴姿で山の斜面を一諸にかけずりまわるのだ。 追いかける対象物の攻撃性が、強くて手こずるほど野生の血がさわいでくる。 魚の身を仕掛け、巣穴をのぞきこみ、煙を噴く筒を巣に入れるなど、機敏に判断しなければ戦利品は得られない。 里に戻るとさっそく、酒を片手に反省会なる飲み会が開かれる。 ピンセットでつまみ出した蜂の幼虫や成虫を、バター炒め・唐揚げ・蜂の子飯などと山人は手ばやく料理をする。 女房も子供もその自慢話とともに山のめぐみをいただきつつ、おおいに興じるのである。 この歌は岐阜でのへぼ取りを詠んだ。 土にまみれ、枯葉に足をとられ、崖をそろそろ下りながら自然万物に歩調を合わせて、あらゆる枠組みから解き放されたときに、はじめて人間の素の姿があらわれる。 初句の三韻の「みれば」には、好奇心に満ちた少年の目のかがやきがある。 作者は蜂の坊やをヒト科ヒト属と同列に置き、醤油を浴びて透きとおるのを見ながらじつに機嫌がよい。 原始では生き物はもともと、食うか食われるかの関係に成り立っていた。 私も熊野の山で椎の木のシロスジカミキリ、臭木のコウモリガの幼虫でも見つけたときは、ありがたく食ってやろうかと今からねらっている。 濃淡にまた斑にと陽はわたり椎の切株くふくふ笑う 小黒世茂 『猿女』 |
| [BACK] |